
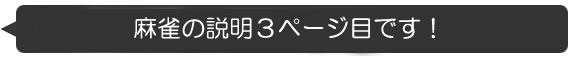
| TOP > 麻雀説明 > 3ページ目 |
| 1ページ目 | 2ページ目 | 3ページ目 | 4ページ目 |
| ・麻雀とは ・ゲームの目的 ・麻雀牌 ・点棒 |
・面子(メンツ) ・あがりの形 ・待ちの形 ・鳴き(ポン・チー・カン) ・ツモとロン |
・役について ・場について ・ゲーム進行 ・ゲームの終了 |
・チョンボとは ・麻雀用語 |
役について・役は麻雀において超重要です。あがる時は基本、4面子1雀頭であがれますが、役がないとあがる事が出来ません。 その他に複数の役を組み合わせる事で点数アップを狙う事が出来ます。 役は手牌の形の事を指し、ポーカーでいう所のツーペア、フルハウスとかと一緒の概念です。 役の数え方は飜(ハン)と言い、飜数が高いほど、難しく、点数も高くなっていきます。 麻雀役の詳細は役説明で確認できます。 場について・一般的には半荘(ハンチャン)戦が一区切りになってます。東場の東1局からスタートして、オーラスまでが半荘戦になります。
それぞれの局で1人が親、残りの3人が子になります。 親は東家(トンチャ)と呼ばれ、親から反時計回りに南家(ナンチャ)、西家(シャーチャ)、北家(ペーチャ)になります。 ゲーム進行1.開始前に準備として点棒を均等に配ります。一般的には25000点ずつが多いです。2.場所決めです。決め方は複数ありますが、一般的なものを1つ説明します。 3.牌を積みましょう。自分の列に17列の2段(34枚)が基本です。 尚、積み終わったら山(積んだ牌を言います)の全体を右前に出してあげましょう。対面の人が牌をとりやすくなります。 4.次は最初の親(起家と言います)を決めましょう。 先程の2.場所決めの際に 仮仮親がサイコロを2つ振ります。 その2つのサイコロの目を足して、サイコロを振った本人から反時計周りに数えます。 数えた位置に当たる人が仮親になります。 今度は仮親がサイコロを2つ振り、同様に反時計回りで数えた位置に当たる人が起家(最初の親)になります。 2つサイコロを足した目が5、9なら東家(自分)、2、6、10なら南家(右の人)、3、7、10なら西家(対面の人)、4、8、12なら北家(左)の人と覚えておくと楽でしょう。 場所の語呂覚え 右2(うに) 対3(といさん) 左4(さし) 自5(じご) 右6(うろく) 対7(といなな) 左8(ひだりっぱ) 自9(じく) 右10(うじゅう) 対11(といじゅういち) 左12(ひだりじゅうに) 5.ゲームスタート。配牌の配り方と嶺上牌とドラ表示牌 親が2つのサイコロを振ります。 場所決めと同じ要領で6なら右の南家の配牌から持ってきます。その時に左から6列残して、4牌ずつとっていきます。 (例) サイコロの目が7の場合は対面の西家の配牌で左から7列残して、4牌ずつとっていきます。  ※雀龍門2の画像を引用させて頂いてます。 その後、とった牌から時計回りに南家、西家、北家の順に4牌ずつとっていきます。 それを全員が3回繰り返します。(4枚×3回=12枚) 最後に1枚ずつとり手牌を13枚にします。 その時に親は14枚目の牌(第1ツモ)を一緒にとってくるのが一般的です。(一般的にちょんちょんと言います) その後にドラ表示牌をめくります。ドラ表示牌は最後から3列目の牌です。 ドラはドラ表示牌の次牌になります。  最終列の上段の牌(嶺上牌)を左の下に下ろしてますが、牌を落とさない為に下ろすのが一般的です。 まず、東家が配牌14牌の中から不要だと思う1枚を場に捨てます。 次に南家が1牌ツモって、不要牌を1枚を場に捨てます。 西家、北家も同様に1牌ツモって、1枚を場に捨てます。 これを誰かが上がるか流局(麻雀牌を14枚残し)するまで続けます。 親があがるか、聴牌していない場合は次の局へ進みます。 ゲームの終了・オーラス(南4局)が終了するか、誰かの点数がなくなったら、半荘戦終了です。(一部点数がなくなっても続行するルールもあります)尚、オーラスの親があがった時にその親が1位なら連荘せずに終了する事も出来ます。(ルールによっては続行もあります) ← 2ページ目 【麻雀説明 3/4ページ】 4ページ目 → |
||||||||||||
| 麻雀説明 | ルール | 役 | 点数・得点計算 | 牌効率・手牌考察 TOP | サイト運営者 | サイトマップ | イカサマ技 | 素材 |
Copyrights(c) 2011 麻雀やろう All Right Reserved. |